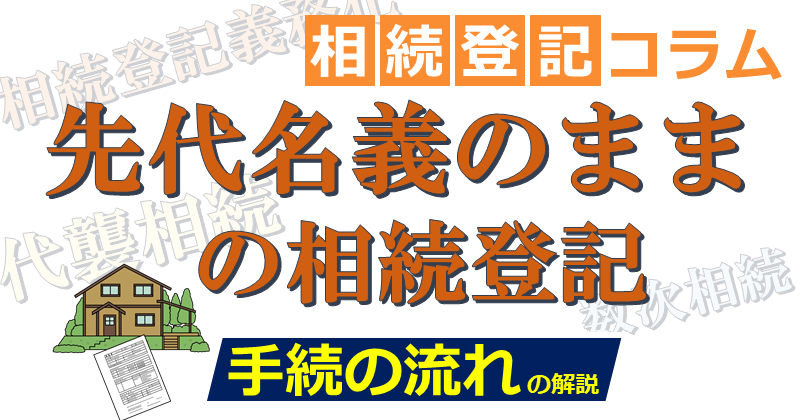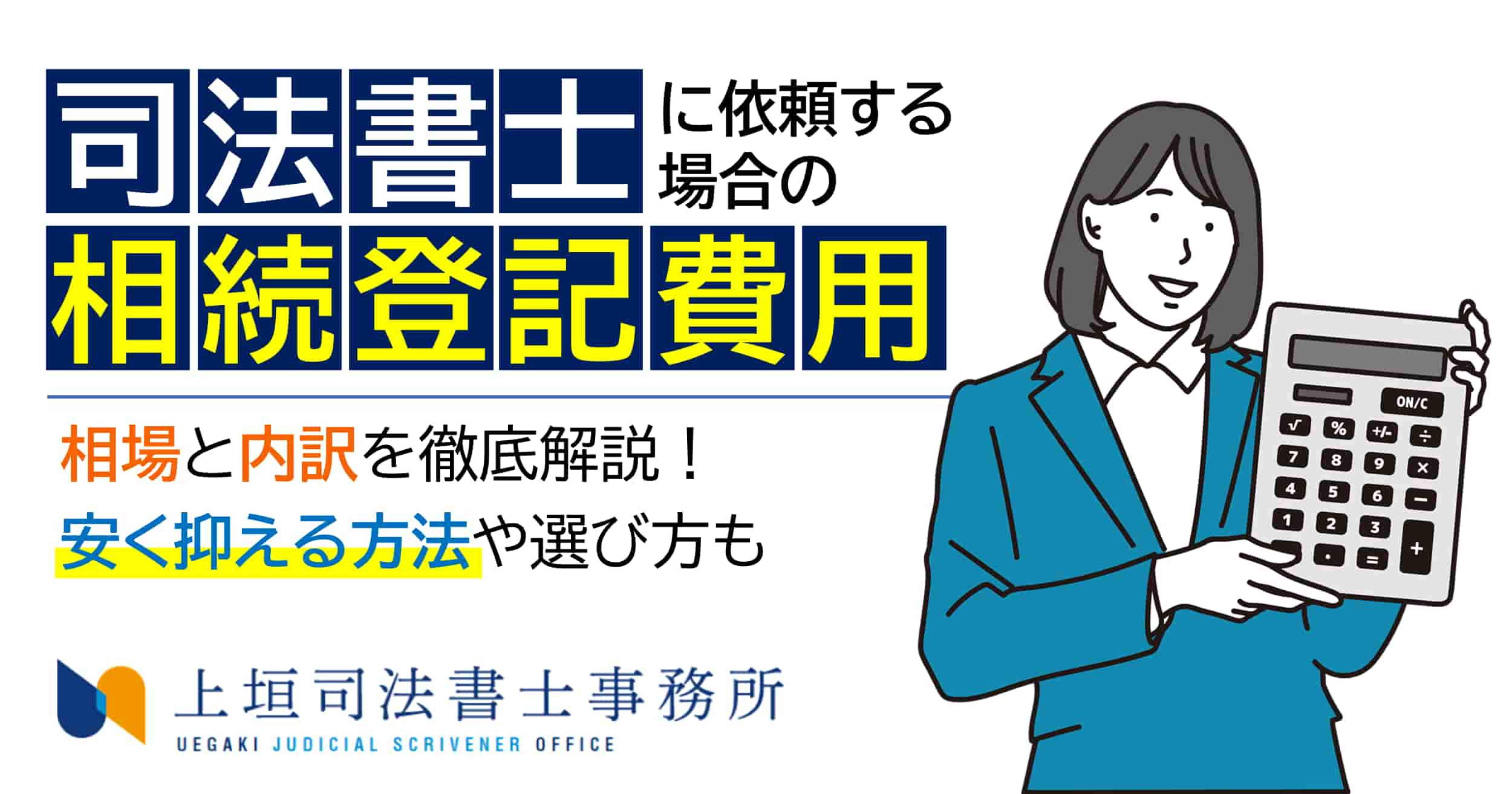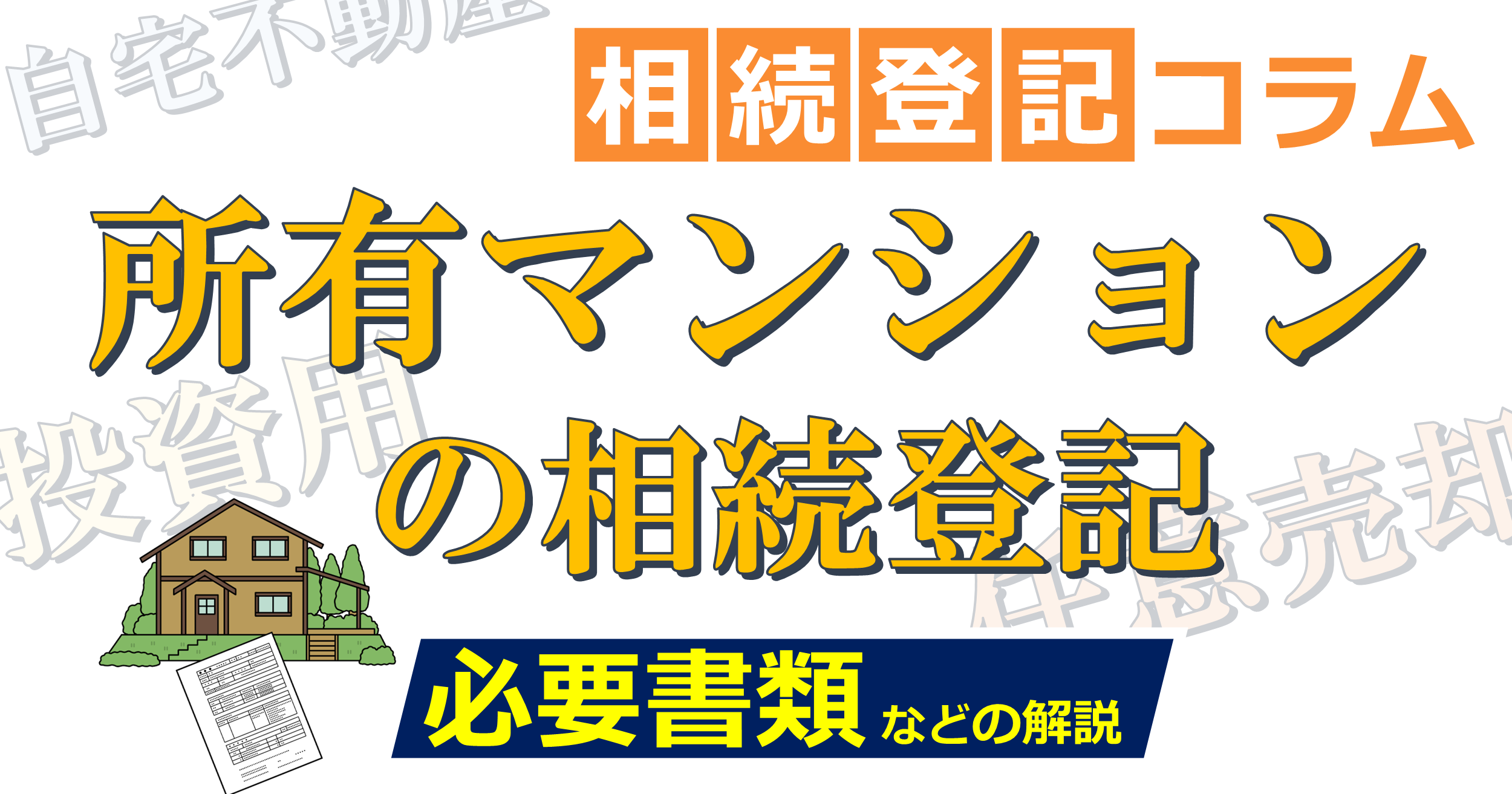相続登記をしないとどうなる?相続登記の放置リスクと対策を徹底解説
登記手続
執筆者 司法書士 上垣 直弘
- 兵庫県司法書士会登録番号 第1549号
- 簡易裁判所訴訟代理認定番号 第712178号

日頃、東播磨地域(明石市、加古川市、高砂市、稲美町、播磨町)や淡路市、神戸市にお住まいの個人、中小企業の方から不動産登記手続を中心に年間100件以上のご依頼を受けています。中でも遺産整理手続の依頼は多く、これまで遺産の名義変更や処分、不動産の相続登記を数多く取り扱った実績があります。
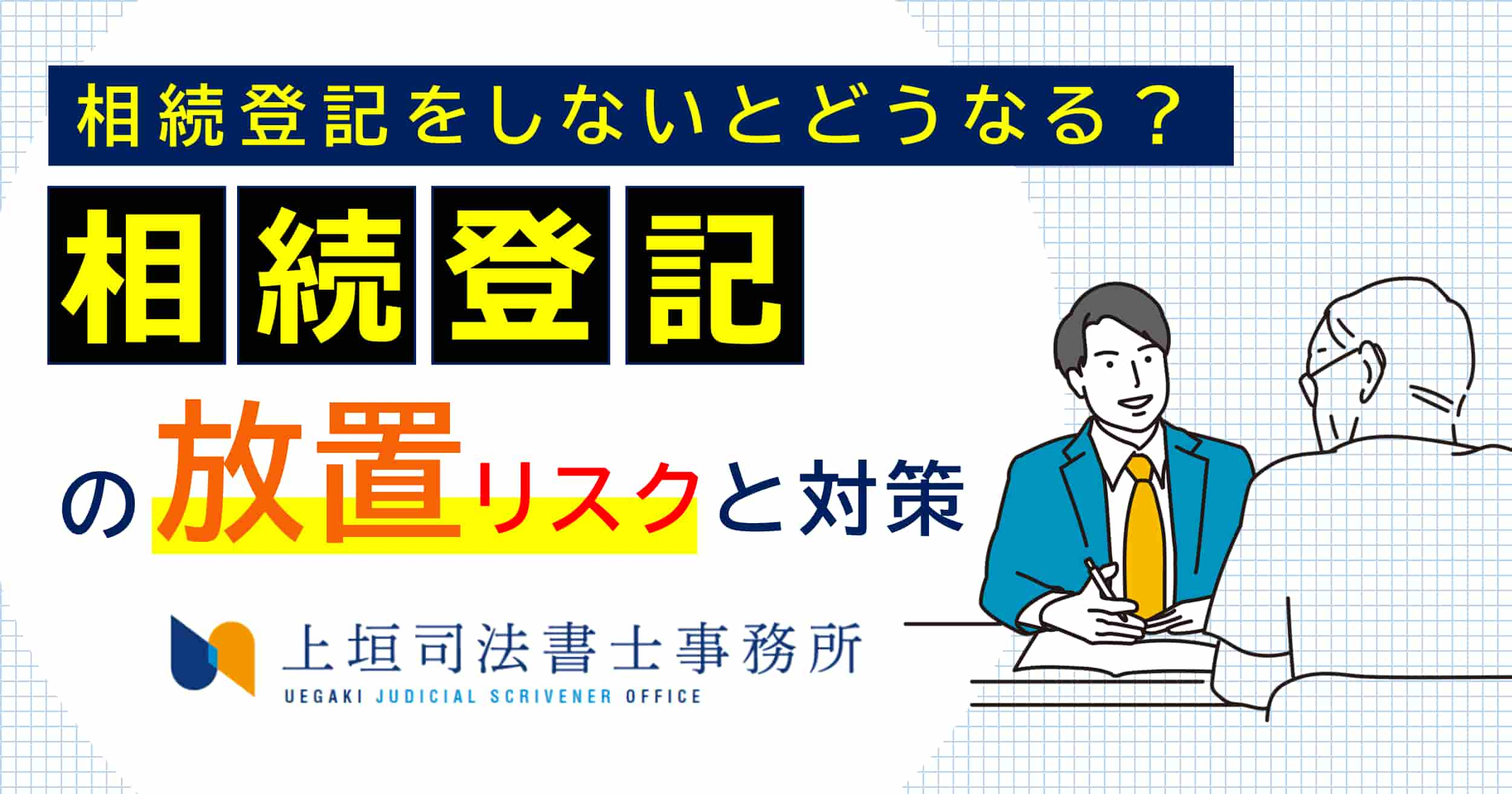
目次
- 相続登記をしないとどうなる?相続登記の放置リスクと対策を徹底解説
- 1. 相続登記の基本と制度改正の背景
- 1-1. 相続登記とは何か?不動産の名義変更の重要性
- 1-2. なぜ今、義務化されるのか?所有者不明土地問題の深刻化
- 2. 相続登記義務化の概要
- 2-1. 義務化の開始日と猶予期間:2024年4月1日から3年以内の申請
- 2-2. 10万円以下の過料(罰則)はどう適用される?
- 2-3. 過去の相続分も対象になる点に注意
- 3. 相続登記をしないと直面するリスク
- 3-1.相続登記義務の違反による罰則
- 3-2. 不動産を売却・担保設定できなくなる
- 3-3.税制上の優遇措置を受けられなくなる
- 3-4. 他の相続人の債務で差し押さえられる可能性がある
- 3-5. 相続人の数が増え権利関係が複雑化
- 3-6. 必要書類の入手が困難になり手続きが長期化
- 3-7. 固定資産税・都市計画税が想定外に高額になることも
- 3-8. 空き家問題や公共事業への影響や、損害賠償請求のリスク
- 4. 相続登記手続きの流れと全体像
- 4-1. 登記事項証明書で不動産の現状を確認
- 4-2. 被相続人・相続人の戸籍謄本など必要書類の収集
- 4-3. 遺産分割協議と協議書の作成
- 4-4. 登記申請書の作成と法務局への提出
- 5. 相続登記ができない場合の救済策
- 5-1. 相続人申告登記の新設|すぐに相続登記できない時の対処法
- 6. 相続登記にかかる費用の目安
- 6-1. 登録免許税・戸籍収集など必須の実費
- 6-2. 司法書士に依頼するときの報酬相場
- 7.専門家選びで確認したいポイント
- 7-1. 難解な書類作成や複雑な相続関係の整理をプロに任せられる
- 7-2.相続人間のやり取りを任せられる
- 8. まとめ|相続登記の放置はリスク大、早めの対応が安心
相続登記をしないとどうなる?相続登記の放置リスクと対策を徹底解説
相続によって不動産を取得した場合、登記名義の変更をすることが基本です。
登記して初めて新所有者は第三者に対して権利を主張することができるため、土地の利用や取引をおこなう上でとても重要です。
相続登記をしないでいる場合、次のリスクがあります。
② 【土地活用ができない】 売買、金融機関の融資がおこないづらい
③ 【税申告の優遇が不適用】 相続不動産の売却が遅れると特例適用が受けられない
④ 【他相続人の影響を受ける】 他相続人の借金で差押えを受ける可能性
⑤ 【相続登記が複雑になる】 相続が繰り返され相続人が増えてしまう
⑥ 【登記必要書類が入手が困難になる】 公的書類の保存期間を経過すると入手できない
⑦ 【税金が高額になる】 特定空き家認定で高額な税金請求のリスクがある
⑧ 【損害賠償請求を受ける】 管理不動産が原因で怪我をさせると賠償リスクがある
相続登記をしないままでいると、不動産の売却や、相続した不動産を担保としてローンや融資を受けることも難しくなるといったリスクがあります。
本記事では、相続登記が義務化された背景や具体的な手続き方法、放置した場合のリスクなどを整理し、適切な相続登記手続きについて解説します。
1. 相続登記の基本と制度改正の背景
まずは相続登記や制度改正の全体像を整理し、義務化に至った背景を把握することから始めましょう。
相続登記とは、不動産を相続した際に、新しい所有者を正確に公示するために必要な手続きです。
これまでは相続登記をするかどうかは任意とされてきましたが、未登記のため所有者不明の土地が増えている社会的背景もあって、2024年4月1日から義務化されました。
参考記事
- 特集ページ│相続登記の義務化相続登記義務化にあたり制度趣旨や制度化された背景、相続登記義務違反に対する罰則などについて解説したコラムです。
1-1. 相続登記とは何か?不動産の名義変更の重要性
相続登記とは、不動産の所有者が亡くなったときに、その不動産の名義を相続人に変更する手続きのことです。
相続による所有権の移転登記をしなければ、登記簿上の所有者が被相続人のまま残り、実際の利用や管理がスムーズにおこなえない場合があります。
特に相続した土地建物などの不動産を売却したり、これらを担保として金融機関からの借入(融資)を検討する際、新所有者への相続登記が完了していなければ、取引が進まない可能性が高くなります。
また、先代の相続登記をおこなわないうちに、次世代の相続が発生するケースなど、相続がくり返し発生すると相続人が増え、権利関係が複雑化するため、最終的に当事者全員の同意を得ることが難しくなり、時間や手間がさらにかかるリスクも大きくなります。
1-2. なぜ今、義務化されるのか?所有者不明土地問題の深刻化
相続登記が長年放置された結果、所有者が明確でない土地が全国で増加してきたことが大きな問題とされています。
この所有者不明土地が公共事業や災害復興の障害になるケースが発生し、空き家問題の増加にも拍車をかける状況です。
こういった社会的コストを抑制するために、相続登記の義務化が打ち出され、2024年4月以降は放置できない環境が整えられました。
2. 相続登記義務化の概要
2024年4月1日から相続登記が義務化され、期限や罰則が新設されました。
該当する方は早めに内容を確認しましょう。
相続登記の義務化は、不動産を取得相続した人が、相続により取得したことを知った日から一定期間内に名義変更の申請を行うことを求める制度です。
期限内に手続きをおこなわない場合、過料という形で罰金が科される可能性があります。
いつまでに何をすべきかを正確に把握し、遅れずに手続きを進めることが大切です。
2-1. 義務化の開始日と猶予期間:2024年4月1日から3年以内の申請
相続登記義務化の施行日は2024年4月1日であるため、その日以降に相続が発生した場合、不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請が必要です。
万が一、相続が発生しているのに相続登記を放置していると、10万円以下の過料が科される恐れがあります。
2-2. 10万円以下の過料(罰則)はどう適用される?
相続登記を義務期間内(不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内)におこなわなかった場合には、10万円以下の過料が科されることがあります(不動産登記法第164条)
なお、相続登記ができないような状況にある場合は、国は相続登記の義務を負う相続人が、法務局(登記官)に「不動産の登記名義人の相続人である」ことを申し出ることで、相続登記義務を果たしたものとみなされる「相続人申告登記」の利用を検討します。
期限内に相続登記がおこなえず、「相続人申告登記」の利用が考えられるケースは次のものがあります。
② 遺産分割協議や遺言の有効性などで揉めているため、相続登記できない場合
ただし、相続人申告登記はだけでは、相続人(新所有者)への名義変更をしたことはならないことに注意が必要です。
そのため、相続人間での遺産分割協議が整うなど、相続登記が申請できる状況になった際には、改めて相続登記をおこなう必要があります。
相続人申告登記は、「相続人申出書」に、「被相続人が亡くなったことが分かる戸籍の証明書(戸籍または除籍謄本など)」、「相続人であることが分かる戸籍の証明書(戸除籍謄本等など)」や、「被相続人の登記上の住所」が「戸籍の証明書に記載された本籍」と異なる場合には「住民票(除票や戸籍の附票)の写し」を付けて、相続不動産を管轄する法務局の窓口へ持参・郵送して提出します。
なお、相続人申告登記は、申出をした相続人のみが相続登記の義務を果たしたことになります。
そのため、相続人となる方がそれぞれに申出をする必要があることに注意が必要です。
参考記事
- 「相続人申告登記」とは?相続登記義務違反を一時的に回避する方法を解説
相続登記の義務を負う相続人が、法務局(登記官)に「不動産の登記名義人の相続人である」ことを申し出ることで、相続登記義務を果たしたものとみなされる「相続人申告登記」制度について解説しています。
2-3. 過去の相続分も対象になる点に注意
2024年(令和6年)4月1日以降、新たに施行されたこの法改正は、将来の相続だけでなく、すでに発生している相続にも影響する点に注意が必要です。
施行日前の令和6年3月31日以前に発生した相続等などにより不動産を取得した場合、令和9年3月31日までに登記をおこなう必要があります。
3. 相続登記をしないと直面するリスク
相続登記の放置は、経済的な利益や資産管理に大きな影響を及ぼす可能性があります。
相続登記を怠ると、過料というペナルティにとどまらず、不動産自体を売却したり、融資を受ける際の担保に使えないといった不便が生じることがあります。
また、時間が経てば経つほど相続関係は複雑になり、相続人同士の話し合いが難航し、相続トラブルのリスクもまた増えていくでしょう。
以下の項目を確認し、放置のデメリットを改めて認識しておきましょう。
3-1.相続登記義務の違反による罰則
不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内に、正当な理由なく相続登記をおこなわない場合、10万円以下の過料が科されるリスクがあります。
参考記事
- 相続登記義務に違反したらどうなる?(令和6年4月1日以降、罰則あり)
正当な理由がなく相続登記をおこなわない場合、国などの行政からの罰金である「過料」を受ける可能性があります。事例を交えながら、どのような場合に罰則を受けるのか。罰則を受ける場合、どのような流れで手続が進むのかについて司法書士が解説しています。
3-2. 不動産を売却・担保設定できなくなる
相続登記が完了していない不動産は、登記簿上は被相続人の名義となっているため、第三者との売買契約や金融機関での担保設定がスムーズに行えません。
例えば、不動産売却の際、登記簿上の名義人が被相続人等などの名義だと、そのまま買主に移転登記をすることはできません。
したがって、事前に不動産の所有者であるかどうか登記事項証明書を取得し、確認することが一般的です。登記名義を変更していない場合、適切なタイミングで売却ができなくなるリスクがあります。
また、上記売却のケースと同様に、銀行などの金融機関から融資を受ける際に、相続登記がされておらず、亡くなった方の名義のままでは抵当権などの担保権を設定することはできず、融資を受けることができない可能性があります。
以上のように、実際に活用しようとしたタイミングで相続登記がされていないなど、登記上の不備が発覚すると、買い手や融資先との交渉が長引く一因にもなります。
3-3.税制上の優遇措置を受けられなくなる
相続不動産を売却する際に適用を受けられる税制上の優遇措置があります。
- 相続税の取得費加算の特例
相続または遺贈により取得した土地、建物などを相続開始のあった日の翌日から相続税の申告期限(10か月)の翌日以後3年を経過する日までに譲渡する場合に受けられる特例です。 - 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例
相続や遺贈により取得した、被相続人の居住用家屋または居住用家屋の敷地等などを取得し、被相続人が死亡した日以後3年を経過した日の属する年の12月31日までに売却するなど、一定の要件に当てはまるときは、譲渡所得の金額から最高3,000万円までを控除することができる特例です。
売却のタイミングが遅れると特例の適用が受けられません。
また、こうした特例には期間が設けられていたり、一定の要件に当てはまることが必要なケースもあり、税務の専門家である税理士に確認しておくと良いでしょう。
3-4. 他の相続人の債務で差し押さえられる可能性がある
相続登記をしないままにしておくと、法定相続分の共有状態が続き、他の相続人が抱える借金返済のトラブルに巻き込まれるケースがあります。
被相続人名義のままの相続不動産について、他の相続人の債権者により「債権者代位登記」がなされ、不動産の差押えを受ける可能性があります。
この場合、共同相続人の債権者代位権による登記と差押えの対象は、原則として債務者である相続人の法定相続分に対応する持分に限られます。
共有持分が差し押さえられると、最終的に競売にかけられるリスクがあります。
こうした面倒なトラブルに巻き込まれる可能性があるため、早めに登記名義を変更しておきましょう。
3-5. 相続人の数が増え権利関係が複雑化
相続登記を長期間放置していると、次の世代へと相続が進み、相続人の数が倍増することがあります。
相続関係が複雑になると、一度も顔を会わせたこともないような方と遺産分割協議をしなくてはならないなど、合意を得ることが極めて難しくなり、手続きコストや時間も一気に増えてしまいます。
3-6. 必要書類の入手が困難になり手続きが長期化
相続登記には被相続人の戸籍など多くの書類が必要ですが、長期間放置すると相続人の死亡後、一定期間経過により役所での閲覧が難しくなったりするケースがあります。
例えば、被相続人の住所の遍歴が分かる戸籍の附票について、令和元年6月20日以前は閉鎖後5年保存でした。
そのため、市区町村によっては保存期間経過により廃棄され、取得することができないことがあります。
このように、一定期間経過した書類が取得できないケースがあります。
また、被相続人の出生から死亡までの相続人調査において取得する戸籍謄本などは一ヶ所で揃わないことも多く、放置期間が長いほど必要書類の収集は骨の折れる作業となります。
3-7. 固定資産税・都市計画税が想定外に高額になることも
相続登記をおこなわず、所有者が曖昧な状態だと、自治体からの税金に関する優遇措置や減免を受けられなくなる可能性があります。
また、自治体は相続人のうち一人を代表者として指定する(例えば、固定資産税の納税通知書の送付先として連絡があった人など)などして固定資産税の納付を求めることがあります。
しかし、相続人代表者に納税通知書が送付されたとしても、固定資産税の納税義務は相続人全員が負っています(連帯納税義務)。
そのため、遺産分割協議や遺言書によって不動産を相続しなかった方にとって、新所有者が名義変更登記や納税をしなかった場合に、納税の請求が届く可能性があります。
さらに、自治体から「特定空き家(そのまま放置すると周辺の生活環境に悪影響を及ぼすおそれのある空き家)」として、市町村長から認定されると、住宅用地の特例の適用対象外となるため、高額な固定資産税(6倍)や都市計画税(3倍)を請求されるリスクがあります。
3-8. 空き家問題や公共事業への影響や、損害賠償請求のリスク
相続登記されない不動産が増えると、適切な管理が行われない空き家や放置された土地への不法投棄が発生しやすくなります。
これらの所有者不明物件は、行政が進める公共事業の用地取得の妨げとなったり、防災・減災対策の足かせになったりするなど、社会全体に大きな影響を与えかねません。
また、不動産の管理義務があるため、老朽化した建物が崩れるなどして第三者に怪我を負わせた場合には、損害賠償請求を受ける可能性もあります。
4. 相続登記手続きの流れと全体像
相続登記は複数のステップを経て完了します。
書類収集や法務局への申請など、段階的に進める必要があります。
全体の流れと各ステップをきちんと理解しておくことで、後戻りすることなくスムーズに進められるでしょう。
4-1. 登記事項証明書で不動産の現状を確認
まずは法務局で登記事項証明書(全部事項証明書)を取得し、相続対象の不動産が誰の名義で登記されているか、また、抵当権など第三者の権利が設定されていないかなど、現在の状況を確認しましょう。
複数の不動産を相続した場合は、全ての登記事項を把握しておくと、後の手続きで不備を減らすことにつながります。
4-2. 被相続人・相続人の戸籍謄本など必要書類の収集
相続登記には、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本や、相続人全員の戸籍・住民票など、多岐にわたる書類が必要です。
なお、戸籍については、被相続人や相続人の本籍地のある市区町村役場で取得できます。
書類の不備があると登記申請が受理されない可能性があるため、早めに必要書類のリストを確認し、不備なく揃えておきましょう。
参考記事
- 相続登記申請の必要書類と取得方法を解説【申請パターン別、準備・提出から原本還付までの流れ】 相続登記申請の必要書類について、(1)遺言書、(2)遺産分割協議、(3)法律どおりに不動産を相続する場合に分けて司法書士が 解説します。
4-3. 遺産分割協議と協議書の作成
生前に遺言書を残しておらず、法定相続分どおりに相続をしない場合、相続人全員による遺産分割協議をおこなう必要があります。
遺産分割協議は相続人全員が参加する必要があり、全員が参加せずにおこなった遺産分割協議は法律上無効です。
相続人調査のうえ、相続人は誰か確定しておくことが重要です。
協議自体は口頭でも可能ですが、不動産の相続登記には遺産分割協議書を法務局へ提出する必要があるため書面で作成しておく必要があります。
登記申請時の必要書類となるので、協議に参加した相続人全員の実印や印鑑証明を添付し、作成しておきましょう。
参考記事
- 法務局の遺産分割協議書のひな形(ダウンロード可能・Word/Excel/PDF版)で解説する「相続登記申請」 法務局ホームページで公開されている遺産分割協議書のひな形(サンプル)をもとに、相続登記申請について登記手続きの専門家である司法書士が解説します。
法務局の遺産分割協議書のテンプレート、その登記申請書のサンプルもダウンロードできるWord/Excel/PDFファイルをご用意しました。
4-4. 登記申請書の作成と法務局への提出
最終的に、不動産を管轄する法務局へ登記申請書を提出し、申請書類が受理されてから審査のうえ相続登記が完了します。
参照リンク
登記申請書の書き方には決まりがあるため、不安がある場合は司法書士や法務局の相談窓口を利用するとミスを減らし、スムーズな申請が可能です。
5. 相続登記ができない場合の救済策
相続人全員が揃わないなど、すぐに相続登記の申請を完了できない場合は別の制度を活用することも検討できます。
相続登記の手続きが難航する場合でも、完全に手立てがないわけではありません。
相続人未確定のまま放置すると相続登記の義務違反を招きかねないため、一時的に罰則を回避する方法を紹介します。
5-1. 相続人申告登記の新設|すぐに相続登記できない時の対処法
相続人申告登記とは、まだ正式な相続登記ができない場合でも、相続人の情報を先に法務局に申告する制度です。
これにより、一旦は申請義務を履行した形となり、不動産の相続内容が確定したのち正式な相続登記をおこないます。
この相続人申告登記は、共同相続人が複数いる場合でも単独でおこなうことができます。
反対に言えば、共同相続人はそれぞれが相続人申告登記をおこなわなければなりません。
ただし、相続人申告登記をおこなったとしても、不動産を売却したいときや担保にしたいときは、最終的には相続登記が必要になるので、できるだけ早めに手続き完了を目指しましょう。
参考記事
- 「相続人申告登記」とは?相続登記義務違反を一時的に回避する方法を解説
相続登記の義務を負う相続人が、法務局(登記官)に「不動産の登記名義人の相続人である」ことを申し出ることで、相続登記義務を果たしたものとみなされる「相続人申告登記」制度について解説しています。
6. 相続登記にかかる費用の目安
相続登記では、税金や書類の取得費用など、複数の費用が発生します。
あらかじめ把握しておきましょう。
費用面を事前に把握しておくと、余裕を持った手続き準備が行えます。
特に登録免許税や司法書士への報酬は不動産の評価額や依頼内容によって変わるため、自分のケースでどれくらいになるか確認しておくこと安心です。
6-1. 登録免許税・戸籍収集など必須の実費
相続登記にかかる登録免許税は、不動産の評価額に一定の税率をかけて計算されます。
- 相続人が取得する場合
固定資産税評価額×0.4%(相続による所有権移転登記の税率) - 相続人以外が取得する場合
固定資産税評価額×2%(遺言による贈与(遺贈)による所有権移転登記の税率)
※固定資産税評価額:不動産の価値を評価したもので、毎年市区町村役場から送られてくる固定資産税の納税通知書に記載されています。
また、被相続人や相続人の戸籍・住民票などを取得する費用も合わせて考慮する必要があります。
- 戸籍謄本…450円
- 除籍、改製原戸籍…750円
- 住民票、除票、戸籍の附票…地域によって異なる(数百円程度)
- 印鑑証明書…地域によって異なる(数百円程度)
※ 郵送による請求も可能ですが、郵便局窓口で料金相当分の定額小為替(発行手数料200円/1枚)を購入し同封が必要です。
これらの実費は必ず発生する費用となるため、あらかじめ予算に組み込んでおきましょう。
6-2. 司法書士に依頼するときの報酬相場
相続登記を司法書士に依頼すると、書類作成や法務局での手続きを代行してもらえるため安心です。
しかし、報酬は不動産の評価額や相続人の数、登記の内容により異なります。
事前に司法書士に見積もりを依頼し、対応範囲や費用がいくらかかるかを確認しておくと良いでしょう。
7. 相続登記の手続きを司法書士に依頼するメリット
専門知識が必要な手続きをプロに任せることで、時間や労力、リスクを大幅に軽減できる場合があります。
相続登記では戸籍や遺産分割協議など、書類の多さと手続きの煩雑さに多くの人が負担を感じるでしょう。
法的なミスを防ぎながらスムーズに手続きを進められるため、結果的にトラブルを最小限に抑えられるため、専門家に依頼することをおすすめします。
7-1. 難解な書類作成や複雑な相続関係の整理をプロに任せられる
司法書士に依頼すれば、煩雑な書類作成や相続人調査を効率よく進められるので、個人で行うよりも手間や不安を軽減できます。
相続人同士のトラブルを防ぐためのアドバイスや、書類の不備による申請却下を避けるためのポイントなども得られるため、安心感の大きさがメリットと言えるでしょう。
7-2.相続人間のやり取りを任せられる
登記名義の変更を長年放置していると、連続して相続が発生し、顔も知らない親族が相続人となっているケースがあります。
相続人調査の中で住所地を確認し、連絡を取り事情を伝え、登記名義の変更のための協力をお願いすることに、心理的なハードルは高いと言えます。
司法書士に依頼することで、疎遠な相続人とのやりとりを任せられるため精神的な負担を軽減することができます。
参考コラム
- 相続登記の代行を依頼する前に押さえておきたい基礎知識│相続登記フルサポートの案内
相続登記を司法書士などの専門家に任せることを検討されている方に知っておいて頂きたい基礎知識について、司法書士が解説しています。
8. まとめ|相続登記の放置はリスク大、早めの対応が安心
相続登記を後回しにすると、いつの間にか身動きが取れなくなるほど問題が深刻化する恐れがあります。
相続登記の義務化に伴い、違反による罰則が科される可能性だけでなく、不動産活用の制限や複雑な権利関係の発生が実生活に大きな影響を及ぼします。
早めの登記対応は自身の資産を守るだけでなく、将来的なトラブルの回避にもつながるため、この機会に一度、家族や専門家と協力して手続きを進めることをおすすめします。
上垣司法書士事務所では、相続登記をフルサポートしています。
相続人調査、登記申請に必要な遺産分割協議書の作成、疎遠な相続人への連絡、法務局への申請とやりとりなどお任せいただけます。
長年、相続登記がされないまま放置されて数次相続(何世代にもわたる相続)が発生している事例もあります。
複雑な相続登記についても、ぜひお気軽にお問い合わせください。
税理士や弁護士とも連携しており、ご依頼の際には相続トラブルや相続税申告に関する無料相談のご紹介も可能です。
また、相続手続きに関する相談も実施しています。
相談時に、ご事情を丁寧にお伺いし、解決策や注意点といったアドバイスをさせて頂きます。
相談は有料ですが、ご依頼時にお支払い頂いた相談料を司法書士費用に充当させていただいております(ご依頼の場合、相談料は実質無料となります)。
電話、メールなどで相談予約を受け付けしております。
ご予約の上、ご相談ください。