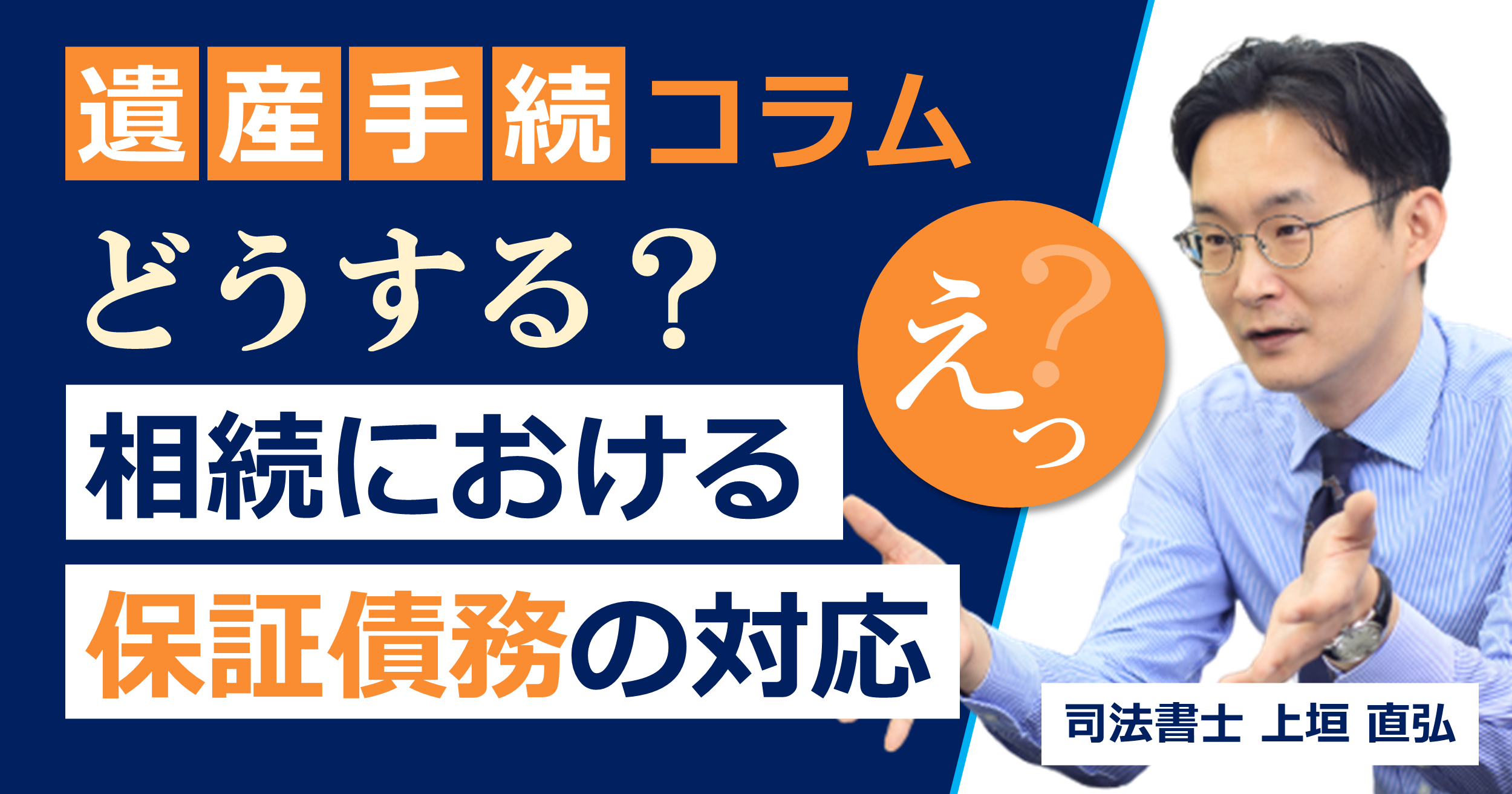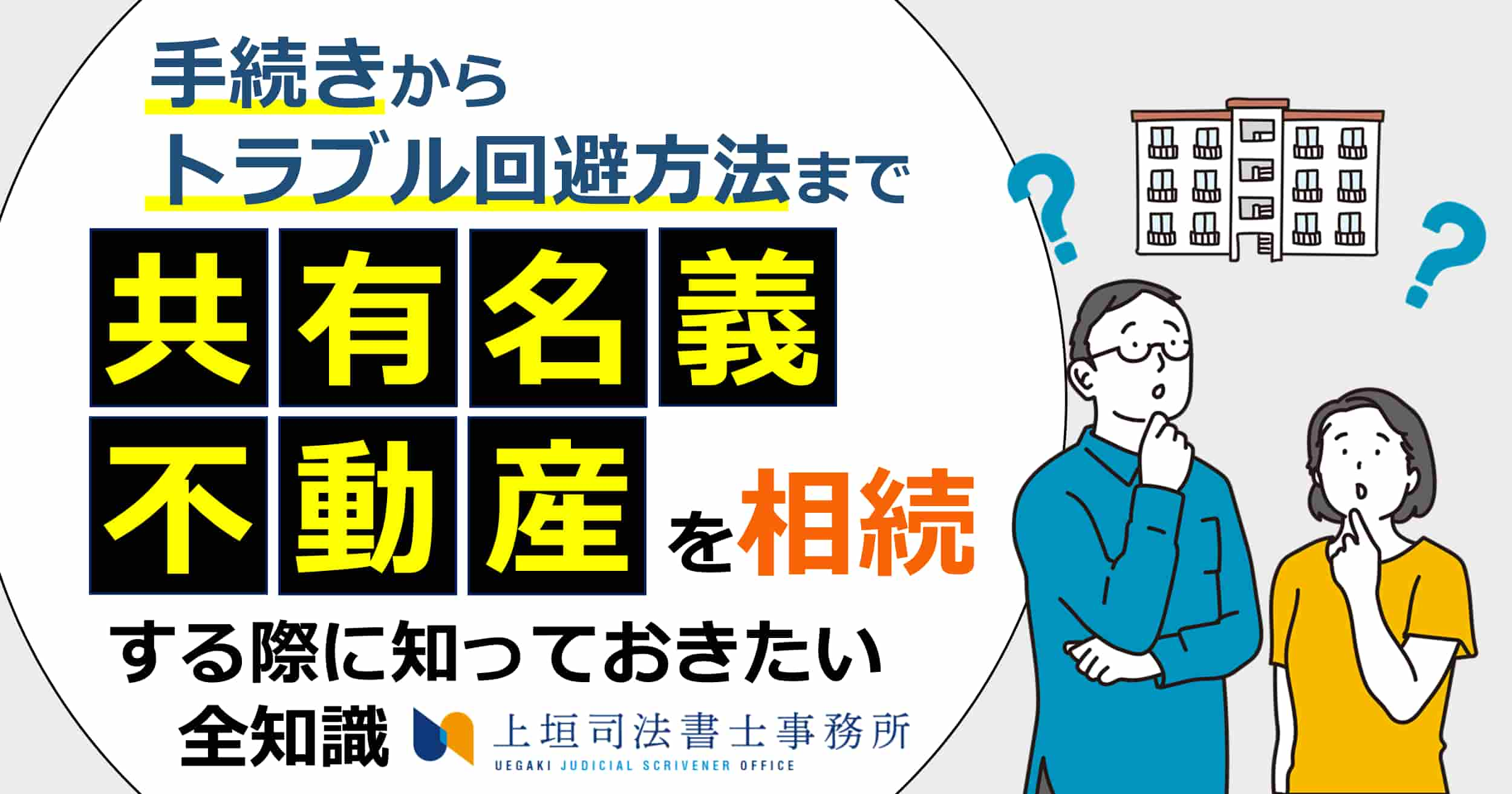【遺言書と公正役場】公正証書遺言のすべて│メリット・費用・手続き完全ガイド
相続手続
執筆者 司法書士 上垣 直弘
- 兵庫県司法書士会登録番号 第1549号
- 簡易裁判所訴訟代理認定番号 第712178号

日頃、東播磨地域(明石市、加古川市、高砂市、稲美町、播磨町)や淡路市、神戸市にお住まいの個人、中小企業の方から不動産登記手続を中心に年間100件以上のご依頼を受けています。中でも遺産整理手続の依頼は多く、これまで遺産の名義変更や処分、不動産の相続登記を数多く取り扱った実績があります。

目次 [ 開閉 ]
【遺言書と公正役場】公正証書遺言のすべて │ メリット・費用・手続き完全ガイド
「自分の死後、家族が遺産分割でもめないようにしたい」
「大切な財産を、自分の望むとおりに、確実に家族へ残したい」
このように考え、希望をかなえる最も確実な方法として「公正証書遺言」を検討している方が増えています。
公正証書遺言は、法律の専門家である公証人が作成します。
そのため、遺言書の信頼性が極めて高く、将来の相続トラブルを防ぐ最も有効な手段の一つです。
しかし、いざ作成しようとすると
「費用はいくらかかるの?」
「手続きはどう進めるの?」
「何から準備すればいい?」
といった多くの疑問に直面します。
本記事では、公正証書遺言の基本知識から、メリット・デメリット、必要書類、具体的な作成手順まで、あなたが知りたい情報を網羅的に解説します。
1. 公正役場で作る遺言書とは?基本知識を押さえよう
公正証書遺言は、全国に約300カ所ある公証役場で、公証人の立会いのもと作成することができる、法的な効力が高い遺言書です。
公証人とは、元裁判官や検察官など長年法律実務に携わった専門家から、法務大臣が任命する実質的な公務員です。
公正証書遺言の作成においては、その法律の専門家が、内容の確認から作成までを全面的にサポートしてくれます。
そのため、形式上の間違いによる無効リスクを限りなくゼロにできるのが大きな特徴です。
自筆で手軽に作成できる自筆証書遺言と比べて費用はかかりますが、原本が公証役場に厳重に保管されるため、紛失・偽造・改ざんのリスクを完全に防ぐことができます。
特に、ご自身の判断能力がはっきりしているうちに作成しておくことで、将来の遺産分割に関する家族の負担を大きく減らすことができます。
財産が多い方や、相続関係が複雑な方ほど、その公的な信頼性の高さが大きな安心につながるでしょう。
1-1. 公正証書遺言とは何か
公正証書遺言とは、法律に定められた方式に基づき、遺言者が公証人と2人以上の証人の前で遺言の内容を口頭で伝え(口授し)、公証人がその真意を正確に文章化して作成する公式な遺言書です(民法第969条)。
まず、公証人は遺言者の話した内容を筆記し、これを遺言者と証人に読み聞かせて内容に間違いがないかを確認します。
次に、遺言者と証人がその内容を承認して署名・押印します。
最後に、公証人が法律に定められた方式に従って作成した旨を記載して署名・押印し、遺言書が完成します。
この厳格な手続きにより、遺言書が無効になるリスクは限りなく低くなります。
完成した遺言書の原本は、原則として公証役場で厳重に保管され、遺言者が亡くなるまで遺言者本人以外に開示されることはありません。
1-2. 自筆証書遺言との違い
自筆証書遺言は、遺言者が全文(財産目録を除く) ・日付・氏名を自書し、押印することで作成する遺言書です(民法第968条)。
費用がかからず手軽に作成できる反面、以下のような大きなリスクやデメリットがあります。
| 比較項目 | 公正証書遺言 | 自筆証書遺言 |
|---|---|---|
| 無効リスク | 極めて低い(公証人がチェック) | 高い(形式不備、内容不明確など) |
| 偽造・改ざん | 不可能(原本を公証役場で保管) | リスクあり |
| 紛失・隠匿 | なし | リスクあり |
| 家庭裁判所の検認 | 不要 | 原則として必要 |
| 費用 | かかる | 原則無料 |
| 証人 | 2人以上必要 | 不要 |
特に大きな違いは、相続開始後の家庭裁判所による「検認」手続きの要否です。
検認手続きとは、家庭裁判所が、自筆の遺言書の状態を公式に確認・保存し、相続人全員にその存在と内容を知らせるための手続きです。
遺言書の偽造・変造や隠されることを防ぎ、相続手続きの透明性を確保するのが目的です。
そのため、遺言書が法的に有効か無効かを判断する手続きではありません。
自筆証書遺言は、発見した相続人などが家庭裁判所に提出して検認を受けなければならず、相続人にとって時間と手間がかかります。
一方、公正証書遺言は検認が不要なため、相続開始後すぐに預貯金の解約や不動産の名義変更といった遺産相続手続きに移ることができ、残された家族の負担を大幅に軽減できます。
なお、令和2年(2020年)からは、自筆証書遺言を法務局で預かってもらう「自筆証書遺言書保管制度」が始まりました。
この制度を利用すれば、紛失や改ざんのリスクを減らし、検認も不要になります。
ただ、遺言内容の法的な有効性(内容の不備)までを法務局がチェックしてくれるわけではありません。
内容の正確性・確実性を担保したい場合は、やはり公正証書遺言が最も優れた選択肢と言えます。
1-3. 公正役場での作成の特徴
公正役場で作成する最大の特徴は、法律の専門家である公証人が遺言書の作成をおこなう点です。
遺言者の意思(誰に、どの財産を、どのくらい渡したいか)を丁寧にヒアリングし、それが法的に実現可能か、将来遺産分割協議などで トラブルになる可能性はないかを専門家の視点からアドバイスしてくれます。
また、公証役場は全国どこでも利用可能です。
必ずしも自分の住所地の役場である必要はなく、都合の良い場所や、信頼できる公証人がいる役場を指定して作成することができます。
事前に電話などで予約し、必要書類の確認や打ち合わせをおこなうことで、作成日時を決め、当日の手続きをスムーズに進めることが可能です。
2. 公正証書遺言を作成するメリットとデメリット
公正証書遺言はメリットが多い一方で、いくつか注意すべき点もあります。
両方を正しく理解し、ご自身の状況に合っているかを判断しましょう。
2-1. 【メリット1】 信用性と安全性
公正証書遺言は、公証人が遺言者の本人確認を厳格におこない、遺言者の判断能力や遺言内容が本人の真意にもとづくものであることを確認した上で作成します。
そのため、後日、他の相続人から「本人の意思ではなかった」「無理やり書かれたのではないか」といった主張が出されたとしても、その有効性が覆ることはほとんどありません。
この法的な証明力の高さが、相続トラブルを防ぐ最大の力となります。
2-2. 【メリット2】 遺言書の紛失リスクが低い
自筆証書遺言は自宅で保管することも多く、紛失や、相続人によって破棄・隠匿(いんとく)される恐れがあります。
その点、公正証書遺言は原本が公証役場に半永久的に保管されます。
具体的には、遺言者の死亡後50年、公正証書遺言作成後140年または遺言者の生後170年間保存するという運用をおこなっています。
遺言者が受け取る正本・謄本を万が一紛失しても、公証役場に請求すれば再発行が可能であり、遺言の内容が失われることは決してありません。
2-3.【メリット3】 相続発生後の手続きがスムーズ(検認不要)
前述の通り、公正証書遺言は家庭裁判所での検認が不要です。
これにより、相続人は煩雑な検認手続きを省略でき、不動産の名義変更や預貯金の払い戻しといった相続手続きを迅速に進めることができます。
残される家族への負担軽減という点で、これは非常に大きなメリットです。
2-4. 【デメリット1】 費用がかかる
公正証書遺言の作成には、法律で定められた公証人への手数料が必要です。
手数料は、相続させる財産の価額に応じて決まります。
財産が多ければ多いほど費用も高くなるため、原則無料の自筆証書遺言と比べると費用負担が発生する点がデメリットです。
ただし、将来の遺産分割協議で紛争が起きた場合の弁護士費用などを考えれば、トラブル予防のためのコストとして十分に価値があると言えるでしょう。
2-5. 【デメリット2】 証人2名の立ち会いが必要
公正証書遺言の作成時には、証人2人の立会いが民法で義務付けられています(民法第969条1号)。
そして、以下の者は証人になれません(民法第974条)。
- ✓ 未成年者
- ✓ 推定相続人(遺言者の配偶者、子、親など)およびその配偶者、直系血族
- ✓ 受遺者(遺言によって財産をもらう人)およびその配偶者、直系血族
- ✓ 公証人の配偶者、四親等内の親族など
このように利害関係人は証人になれないため、信頼できる友人や知人に頼む場合でも、条件に当てはまらないか確認が必要です。
遺言の内容を他人に知られたくない場合や、適当な人が見つからない場合は、司法書士や弁護士などの専門家や、公証役場で紹介してもらえる証人に依頼する方法があります。
2-6.【デメリット3】 公証人は遺言書作成のみ
公証人は、遺言者の希望を書面に起こし、法的に問題のない形式で作成します。
そのため、遺言内容については遺言者自身で決める必要があります。
また、相続発生後に相続人の間に立って意見の調整などをしてくれるわけではありません。
そのため、まずは弁護士や司法書士に相談して遺言内容を固め、その内容を公証人に公正証書遺言として作成してもらう、という流れが一般的です。
3. 公正証書遺言の作成に必要なもの
公正証書遺言をスムーズに作成するためには、事前の準備が重要です。
ここでは、具体的に何が必要になるのかを解説します。
【はじめに】 公正役場を探して予約する
まずは、遺言書を作成したい公正役場を探しましょう。
日本公証人連合会のウェブサイトで全国の公証役場を検索できます。
お近くの役場や、アクセスの良い役場を選び、電話で「公正証書遺言を作成したい」と伝え、打ち合わせの予約を取ります。
3-1. 身分証や印鑑証明書などの必要書類
公証役場との打ち合わせの際に、具体的に必要な書類の説明があります。
一般的に次の書類が必要となるため、事前に準備しておくと手続きがスムーズです。
| 必要になる人 | 書類の種類 | 備考 |
|---|---|---|
| 遺言者本人 | ① 印鑑登録証明書(発行後3ヶ月以内) | 実印も持参します。 |
| ② 本人確認書類 | マイナンバーカード、運転免許証など顔写真付きのもの。 | |
| ③ 遺言者と財産を相続させる相続人の戸籍謄本 | ||
| ④ 相続人以外に遺贈する場合、その人の住民票 | ||
| 証人 | ① 証人の本人確認書類 | 運転免許証やマイナンバーカードなど。 |
| ② 証人の認印 | 当日持参します。 |
3-2. 対象財産の資料(固定資産税評価証明書など)
遺言に記載する財産を特定し、その価額を証明するための資料が必要です。
これは公証人の手数料を計算するためにも不可欠です。
- ・ 登記事項証明書(登記簿謄本)
- ・ 固定資産税・都市計画税納税通知書、または固定資産評価証明書
- ・ 通帳のコピー(銀行名、支店名、口座番号、名義人がわかるページ)
- ・ おおよその残高をまとめたメモ
- ・ 証券会社名、銘柄、株数などがわかる取引残高報告書など
これらの資料を基に、事前に「財産目録」を作成しておくと、公証人との打ち合わせが非常にスムーズに進みます。
3-3. 証人の依頼方法
証人2人を自分で手配する必要があります。
前述の通り、推定相続人や受遺者など法律で定められた利害関係人は証人になれません。
信頼できる友人や知人に依頼するのも一つの方法ですが、「遺言の内容を知られたくない」「頼める人がいない」というケースも少なくありません。
その場合は、以下の方法があります。
多くの公証役場では、有料(1人あたり1万円前後が目安)で証人を紹介してくれます。事前に相談してみましょう。
遺言書の原案作成から依頼している場合は、その専門家が証人になることが可能です。
守秘義務があるため、プライバシーの面で最も安心できる方法です。
費用は依頼された事務所によって異なります。
4. 公正役場での公正証書遺言の作成手順
公正証書遺言の作成は、おおむね以下の流れで進みます。
4-1. ステップ1:原案作成と公証人との事前打ち合わせ
まず、ご自身の希望(誰に、何を、どのように残したいか)をまとめた遺言書の原案(メモ書きで可)と、集めた必要書類を持参し、予約した日時に公証役場へ行きます。
公証人は、その原案と資料を基に、遺言者の意思が法的に問題なく実現できるかを確認し、遺言書の正式な文案について打ち合わせをおこないます。
4-2. ステップ2:公正役場へ必要書類を提出
打ち合わせで確定した内容に基づき、公証人が公正証書の案文を作成します。
この段階で、不足している書類があれば後日提出を求められます。
公証人が作成した遺言書案は、作成日より前に郵送やFAXなどで確認させてもらえることがほとんどです。
内容に間違いがないか、自分の真意が正確に反映されているかを最終チェックします。
4-3. ステップ3:署名・押印、遺言書の完成
予約した作成日時に、遺言者本人と証人2人が公証役場に集まります。
公証人が完成した遺言書を読み聞かせ、内容に間違いがないことを全員で確認した後、遺言者、証人、公証人がそれぞれ署名・押印します。
これで公正証書遺言は法的に完成します。
完成後、遺言書の原本は公証役場に保管され、遺言者には正本と謄本が1通ずつ交付されます。
これらは大切に保管してください。
【体が不自由な場合などの出張制度】
病気や高齢で入院中など、やむを得ない理由で公証役場へ行けない場合は、公証人に病院や自宅へ出張してもらうことも可能です。
ただし、その場合は通常の手数料に加えて、日当や交通費などの加算が必要になります。
5. 公正証書遺言の費用・手数料計算方法
公正証書遺言の作成費用は、主に「①公証人手数料」「②その他の実費」に分かれます。
5-1. 手数料と財産評価の考え方
公証人の基本手数料は、遺言によって財産を渡す人ごと、かつ、その財産の価額に応じて、以下の通り法律で定められています。
| 法律行為の目的の価額 | 金額(手数料) |
|---|---|
| 50万円以下のもの | 3,000円 |
| 50万円を超え100万円以下のもの | 5,000円 |
| 100万円を超え200万円以下のもの | 7,000円 |
| 200万円を超え500万円以下のもの | 1万3,000円 |
| 500万円を超え1,000万円以下のもの | 2万円 |
| 1,000万円を超え3,000万円以下のもの | 2万6,000円 |
| 3,000万円を超え5,000万円以下のもの | 3万3,000円 |
| 5,000万円を超え1億円以下のもの | 4万9,000円 |
| 1億円を超え3億円以下のもの | 4万9,000円に超過額5,000万円までごとに1万5,000円を加算した額 |
| 3億円を超え10億円以下のもの | 10万9,000円に超過額5,000万円までごとに1万3,000円を加算した額 |
| 10億円を超えるもの | 29万1,000円に超過額5,000万円までごとに9,000円を加算した額 |
【具体的な計算例】
例えば、妻に6,000万円、長男に2,000万円の財産を相続させる場合を考えてみます。
長男の分 2,000万円 → 26,000円(3,000万円までの区分)
合計手数料 49,000円 + 26,000円 = 75,000円
さらに、全体の財産額が1億円以下の場合は、上記の合計額に13,000円が「遺言加算」 として加算されます。
したがって、このケースの最終的な基本手数料は 75,000円 + 13,000円 = 88,000円 となります。
この他に、正本・謄本の作成費用など(枚数に応じて数千円程度)がかかります。
5-2. 複数の財産がある場合の注意点
遺産が不動産、預貯金、株式など多岐にわたる場合は、それぞれの評価額を算出し、相続させる人ごとに合算して手数料を計算します。
計算が複雑になるため、正確な費用は打ち合わせの際に公証人に確認するのが最も確実です。
6. 遺留分や相続人とのトラブルを避けるために
法的に完璧な公正証書遺言を作成しても、内容次第ではトラブルの火種が残ることがあります。
6-1. 遺留分とは何か
遺留分とは、兄弟姉妹を除く法定相続人(配偶者、子、親など)に法律上保障されている、最低限の遺産の取り分です。
例えば、「全財産を長男に相続させる」という遺言は有効です。
しかし、他の相続人は、自分の遺留分(法律で認められている最低限の相続分)を侵害されている場合、侵害している人に対して金銭の支払いを請求(遺留分侵害額請求)することができます。
この例では、遺留分を侵害された配偶者や他の子どもたちが、長男に対して遺留分侵害額請求をおこなう可能性があります。
6-2. 専門家に相談するメリット
弁護士や司法書士などの専門家は、単に遺言書作成の申請を代行するだけではありません。
将来起こりうる相続人間のトラブルを予測し、それを未然に防ぐためのアドバイスを提供します。
特に、遺留分に配慮した財産配分の提案や、特定の相続人に多くの財産を渡したい理由などを遺言書の「付言事項」として記載し、他の相続人の感情に配慮する、といった細やかな対応は、専門家ならではの価値です。
円満な相続を実現するためには、専門家への相談が非常に有効です。
7. 公正証書遺言に関するよくある質問(Q&A)
公正証書遺言に関する相談で、よく寄せられる質問をまとめました。
Q1. 作成した遺言書の内容を後から変更・撤回できますか?
A1. はい、いつでも可能です。
遺言者は、以前の遺言と抵触する内容の新しい遺言書を作成することで、前の遺言の一部または全部を撤回できます(民法第1022条、第1023条)。
変更する場合も、再度、公正証書で作成するのが最も安全です。
Q2. 公正証書遺言を作成したことは、相続人に知らせておくべきですか?
A2. 必ずしも知らせる必要はありません。
しかし、相続発生後に誰も遺言書の存在に気づかないリスクを避けるため、信頼できる相続人の一人や、遺言執行者に指定した人に、遺言書を作成し公証役場に保管している旨を伝えておくと安心です。
Q3. 遺言書は一度作ったら、見直さなくても大丈夫ですか?
A3. 定期的な見直しをお勧めします。
結婚・離婚、子の誕生、財産状況の大きな変化など、ライフステージが変わった際には、遺言書の内容が現状に合っているかを確認し、必要であれば変更を検討しましょう。
8. まとめ:公正証書遺言を活用し、安心な相続を
公正証書遺言は、あなたの最後の意思を最も確実な形で実現し、残された大切な家族を「争続」から守るための、非常に強力な手段です。
作成には費用や手間がかかりますが、家庭裁判所での検認が不要になるなど、相続開始後の家族の負担を大幅に軽減できるという大きなメリットです。
自筆証書遺言や法務局の保管制度と比較しても、内容の法的な正確性まで担保される点で大きな安心感があります。
財産の内容や家族構成によって最適な遺言の内容は異なります。
まずは一度、お近くの公証役場や、私たちのような相続に詳しい専門家に相談することから始めてみてはいかがでしょうか。
事前の準備をしっかりおこない、あなたの想いを込めた円満な相続を実現しましょう。
上垣司法書士事務所では、遺産相続問題に関する相談をおこなっています。
事前予約制にて、ご予約を受付けています。
お話を丁寧にお伺いした上で、相談内容に応じたプランをご提案いたします。
お電話または問い合わせフォーム(メール)から面談のご予約が可能です。
せひ、お気軽にお問い合わせください。
また、他士業と連携しており、相続トラブル (弁護士)、相続税申告(税理士)もご相談可能です。
ご依頼いただきました際には、これらの相談もご案内可能ですので、安心してご相談ください。